地方公務員災害補償基金本部との交渉を実施/全国労働安全衛生センター連絡会議

2025年7月10日、昨年に引き続き地方公務員災害補償基金本部(以下、基金本部)との交渉が行われた。同年3月22日付で、予め全国労働安全衛生センター連絡会議議長の名前で要請書を基金に送付し、それに対する回答を当日受ける形で1時間半程度の意見交換を行った。基金本部からは昨年から引き続き総務課平本次長、企画課佐藤課長、補償課からは今回はじめて土橋次長と梅本係長が出席した。
10項目の要請事項
要請事項は、
(1)基金各支部の事務を、民間企業における総務人事部署である職員厚生課の職員などが担っており、申請者が不信感を抱くことが少なくないので、「オンブズパーソン」的な独立した部署が担うようにすること。
(2)精神疾患等の原因が複雑な疾病や、災害であっても請求人と関係者、医師等の見解が異なることを把握した場合は、被災者や家族等からの面談による聴取を必ず行うように通達すること。
(3)基金本部や支部の専門医の氏名を明らかにしない理由を説明すること。少なくとも専門科ごとの人数を明らかにすること。
(4)公務災害申請に上司が協力しない場合には直接基金支部が対応できるということが職員に十分周知されていないので、入職時に全職員に周知することを通達すること。
(5)基金本部審査会における口頭意見陳述について、発言しない代理人の出席を認めないことは明らかに不合理であるので運用を改めること。
(6)公務災害認定事例集を作成して公表すること(とくに公務上疾病)。
(7)石綿疾患について、厚生労働省『石綿ばくろ歴把握のための手引』に示された「石綿に関する作業・類型20 吹きつけ石綿のある部屋・建物・倉庫等での作業(教員 その他)」や実際の認定事例件数を踏まえて、教員の中皮腫などを積極的に公務災害認定すること。
(8)新型コロナウイルスワクチン接種による疾病を発症した職員について、事実上接種が強く勧奨されていた状況をふまえて、原則公務上認定すること。
(9)公務上疾病の調査にあまりにも時間を要している現状を踏まえて、具体的な改善策を明らかにすること。
(10)公務災害の認定基準改正等を議論する専門家のメンバーや議論の内容を開示すること(労災保険であれば、通達改正時には必ず『専門検討会』が公開で開かれて、その報告書が出されることも多い)。
と10項目、さらに個別事案として訓練中に死亡した茨城県の消防士・宮本竜徳さんのご両親から、訴訟を通じてようやく公務上が認められたが、長期間戦ってきたことについて、このような思いをするような遺族が二度と出ないよう以下の申し入れと、障がい特別援護金、遺族特別援護金について追加要請を行った。
個別申請、係争事例に則した要請
<茨城県支部宮本さん>
1 支部審査会や本部審査会が、「医学経験則上」判断すると言いながら、宮本さんの事案に関して支部審査会が照会した専門医の「不整脈原性心筋症であったため、体力錬成、訓練により致死性不整脈を誘発した」、「『本人の素因』よりも5年にわたる『訓練』(環境因子)の要因が十分大きいと言える」という意見を全く無視して、公務外決定とした理由を明らかにすること。
2 「心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上の災害の認定について」(令和3年9月15日地基補第260号)を、宮本さんが裁判によって初めて公務上となったことを受けて、改正すること。具体的には最新の医学的知見に基づく意見を尊重することを明記すること。
追加要求(2025年5月28日)
(1)障害特別援護金と遺族特別援護金の金額の根拠を明らかにするとともに、その引き上げを検討すること。
基金本部の役割は補償の実施であることから、法改正を主体的に行うことはできないが、実施のうえで問題があることを認識してもらうために(1)、(2)の要請が行われたところ、公務災害補償法の条文に従ってそれぞれ運用されている旨の回答がされた。
各項目の回答状況
(3)、(9)、(10)については公務災害調査上の問題点の指摘である。迅速な救済が求められるところ、「公正な審査」の確保に主眼を置いたという回答であった。時間がかかることがあっても、適正な審査をすることに専心しているというのである。しかし問題となるのは、たとえば(3)のように専門医が誰であるのか公開しないことで、実際に公正性が担保されていないのかということが検証されることなくこれまで運営されてきた。昨年の交渉では、「基金本部専門医の名簿ならびに選任基準を開示すること」と要請したが、今年は開示しない理由を求め、「少なくとも専門科ごとの人数を明らかにすること」と加えている。それでも念仏を唱えるかのように「公正な審査の確保のため」と回答してくるため、人数と公正性にどのような関係があるのか改めて尋ね、後日各科の人数については基金本部から回答を得るに至った。
(4)、(5)、(7)、(8)は、審査プロセスにおいて公務災害補償制度が労災補償制度に劣る点を指摘している。(4)はハラスメント事案などに見られる、所属長がハラッサーであるような場合、所属長の確認がなくても請求できる原則を徹底することを求めている。
(7)の石綿ばく露についてもばく露が推認できるものは救済の対象となるべきところ、(3)ともかかわりがあるが、専門医が石綿ばく露の判断まで行うような歪んだ判断がなされてきている。
(8)の新型コロナワクチン接種被害については、昨年同様「医療従事者等以外の職員にかかる新型コロナワクチン接種の公務遂行性について」(令和4年3月7日事務連絡)中の「該当職種は、警察・消防等の公務独自のものであること」の拡大解釈である。これらに対し、基金は労災認定基準に等しく判断をしている旨の回答をした。
(5)は審査会の運営についてであり、少し方向性が違うが、本来幅を持たせて実施すべきところ、頑なに手引の文言にこだわってしまう実態を指摘した。基金本部は、改めて全支部への周知徹底を行ってもらいたい。
(6)で求めた事例集はどのような疾病が公務上と認められるか収集してほしいという申入れであるが「迅速な審査を優先」との回答であった。
基金への申し入れは、昨年に引き続き基金の体制強化、事案の迅速処理化、情報開示を求めているが、たとえば宮本さんの事案について、7年以上かけて訴訟でようやく公務上と認められた。宮本さんの事件こそ、認定プロセスを素直になぞれば誤りなく審査請求時に公務上と認定される事案であったが、これだけ時間がかかったのは、申入れ内容とまったく逆の状態にある基金に問題があるためである。今回の申し入れにおいて、基金として宮本さんに対して謝罪をするべきであるという意見が出たが、これは公務員に謝罪をさせて留飲を下げようという意図ではないし、謝った以上責任を取れ、などと言うつもりもない。本件をどのように今後に活かせるのか、基金に考えてほしいため謝罪をするよう申し入れているのである。
認定事例集についても被災者に認められた疾病と公務との因果関係との判断がどのようになされるか先行事例があることで他の基金支部で発生した事案に関し、迅速な公務上外の判断に資することは間違いないが、それすらできないとなると、敗訴事案からフィードバックを得るようなことも到底できないだろう。
自治体労働者が安心して働ける環境を作っていかなくてはならない立場である基金本部には、処理能力や運営方法にまだまだ限界があるとは思えない。改善のために来年も全国センターとの交渉に臨んでもらいたい。
関西労災職業病2025年9月569号

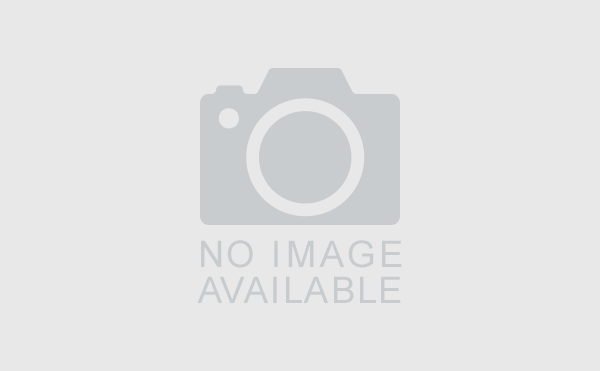
コメントを投稿するにはログインしてください。