2024年度過労死等の労災補償状況公表~右肩上がりのハラスメント事案
複数業務事案は8件
6月25日、厚生労働省は2024年度の過労死等の労災補償状況を公表した。
今回から脳・心臓疾患、精神障害、裁量労働制の補償状況に加えて、複数業務による事案の補償状況も公表された。脳・心臓疾患では6件、精神障害は2件の支給決定があった。本業の給与が安かったり、短時間の就労しかできない場合など、副業を行う労働者は増えている。しかし、労災請求に至る件数は少ない中、複数就労先の労働時間、業務内容の過重性を評価する仕組みはまだまだ不十分であり、複数業務によって過重労働になる事案は増えると思われるが、労災請求につながるのは現状難しそうだ。今後も注目していく。
脳・心臓疾患の労災補償状況は、請求件数1030件、決定件数783件、支給決定件数241件で認定率は30.8%だった。
精神障害の労災補償状況は、請求件数3780件、決定件数3494件、支給決定件数は1055件、認定率は30.2%だった。
コロナ後、増加中

2024年度の脳・心臓疾患については、請求、決定、支給件数ともに、増加した。請求件数は、1023件から1030件で7件、決定件数は667件から783件で116件、支給決定件数は216件から241件で25件増加した(表1-1)。認定率は2023年32.4%、2024年が30.8%で少し下がっている。2021年度に労災認定基準の改定があり、2022年度は32.8%から38.1%へ上がったものの、その後低下している。改定で基準の幅が広がったはずが、決定件数が増加しているにもかかわらず、認定率の改善が見られない。それどころか、死亡事案については、請求、決定、支給決定件数が増加しているにもかかわらず、わずか28.9%の認定率だった。コロナ以前は、死亡事案については、全体平均よりも常に認定率が高く、40%台のこともあったので、これはどういった現象だろうか。
過労死防止法ができて、厚生労働省は力を入れて啓発活動を行っており、労働時間把握や医師による面談指導など対策が取られているにもかかわらず、まだまだ多くの過労死事件が労災認定されないということを、真摯に分析し対策を厳しく見直し、認定基準もさらに実態を踏まえたものに改定するべきだろう。
突出して多い「運輸業」
業種別の状況を見てみる。支給決定件数が1番多かったのは、「運輸業・郵便業」で88件(請求件数213件、決定件数192件)、請求件数は2023年より31件、決定件数は31件、支給件数は13件増加した。2位は「宿泊業・飲食サービス業」で28件(請求件数66件、決定件数61件)、3位は「製造業」24件(請求件数100件、決定件数81件)、4位「その他の事業」22件(請求件数78件、決定件数62件)、5位「卸売業・小売業」20件(請求件数150件、決定件数94件)、6位「サービス業」19件(請求件数117件、決定件数62件)となっている。「運輸業・郵便業」が一番多いのは毎年のことであるが、今回、2位以下がいろいろ変わっている。いつも上位にある「建設業」が今回7位で16件だった。ただ請求件数は23年と変わらず、たまたま認定件数がややすくなかったように思える。「運輸業」以外の業種のほとんどが20数件~20件弱くらいであるので、順位をつけるほどの差があるとは言えない。また前回、認定率は16.9%と低いと言及した「医療・福祉」は、請求件数が97件と例年通り多かったが、決定件数70件で支給件数は10件だったので、認定率は14%とさらに低下した。
職種別で支給決定件数を見ても「輸送・機械運転従事者」が75件(請求件数177件、決定件数169件)で一番多く、うち72件が自動車運転従事者だった。2位は「サービス職業従事者」で34件(請求件数136件、決定件数104件)、3位は「専門的・技術的職業従事者」32件(請求件数149件、決定件数127件)だった。
年齢別では50~59歳が129件(請求件数411件、決定件数310件)でダントツで多く、33件増加した。2位は40~49歳の60件(請求件数213件、決定件数191件)だった。
2023年度の状況でも述べたが、都道府県によって労災の認定率に差がある。
まず支給決定件数で見ると、前回14件で認定率18.6%だった東京が請求件数158件、決定件数136件、支給決定件数44件と、決定件数と支給決定件数を増やして、認定率も32.3%と改善した。次は大阪の支給決定件数35件(請求件数118件、決定件数97件)で認定率は36%で、2023年(24.7%)から10%以上上がっている。支給決定件数も14件増加した。以下は愛知の17件(請求件数72件、決定件数40件、認定率28.3%)、神奈川14件(請求件数78件、決定件数70件、認定率20%)の順だった。兵庫は前年に続いて決定件数28件で支給件数3件、認定率は10.7%と低迷した状況が続いている。請求件数は44件だったので、処理件数も落ちているようだ。
先日の厚生労働省交渉での議題でもあったのだが、厚労省は適切に処理している、と回答するのみできちんと状況を分析しないのは問題である。
時間外労働時間数別では、やはり「80時間以上100時間未満」が支給決定件数が一番多く、80件、次が「60時間以上80時間未満」で46件、「100時間以上120時間未満」40件となっている。160時間以上は16件だった。
ついに1000件突破

精神障害の労災補償状況であるが、これは毎年増加し続けているが、処理できる件数には限りがあるだろうと思っていた。しかし、決定件数は911件、支給決定件数は172件増加し、1000件を超えた(表2-1)。認定率は30.2%で、2023年の34.2%より下がった。
業種別では、「医療・福祉」の支給決定件数が270件で、最多。2023年の219件から51件増加した。請求件数、決定件数もそれぞれ、96件、235件増加した。他の業種と比べて、圧倒的に件数が多いため、先日の厚労省交渉でも理由を尋ねたが、厚労省では原因を探るような分析は行っておらず、ただ負荷となった出来事の「悲惨な事故や災害の体験」と「カスハラ」などによる支給決定が増えているということだった。
以下、支給決定件数が多い順に、「製造業」161件(40件増、請求件数583件、決定件数495件)、「卸売業・小売業」120件、(17件増、請求件数545件、決定件数497件)、「運輸業・郵便業」110件(9件増、請求件数280件、決定件数286件)となっている。順位は前年とほぼ変化はなかった。
職種別では、「専門的・技術的職業従事者」の支給決定件数が300件(請求件数1030件、決定件数956件)で最多。内訳は保健師・看護師が70件、社会福祉専門職業従事者が47件、建築・土木技術者が36件など。やはり医療・福祉分野が多い。2位は「サービス職業従事者」で182件(請求件数556件、決定件数547件)、請求件数は23件減少しているが、決定件数が203件増加しており、支給決定件数も56件増加して、前年2番目に多かった「事務従事者」を上回った。「サービス職業従事者」の内訳は、介護サービス従事者が62件、接客・給仕従事者が43件、飲食調理従事者が35件となっている。3位は「事務従事者」で160件(請求件数796件、決定件数753件)、内訳は一般事務が97件、営業・販売事務が26件となっている。
年齢別の支給決定件数では40~49歳が283件で最多、30~39歳が245件、20~29歳が243件だった。40代が一番多く、次に30代、20代は同じくらい、少し下がって50代だが、20~60歳まで働く年齢層にほとんど偏りなく発症している印象だ。
都道府県格差はつづく
精神障害でも都道府県格差は大きい。またそのときどきの処理状況が数字から推測される。
都道府県別では、やはり支給決定件数が一番多いのは東京で143件、2023年度は決定件数が少なく、処理が追いついていないと考えられたが、2024年度は請求件数763件に対して決定件数は780件と挽回した。しかしながら、支給決定件数は143件なので、認定率は18.3%と少なく、全体の認定率の30.2%とも差が大きい。東京よりも認定率が低かったのは全国でも徳島の16.6%と愛媛14.8%、長崎11.1%の3県のみである。東京以外は支給決定件数が一桁で決定件数も10~20件程度なので比べるのが適切ではなく、東京の低認定率は何が原因か追及するべきだろう。
2位は神奈川で103件(請求件数299件、決定件数268件)、認定率は38.4%で前年に比べて14%も上がった。3位大阪で85件(請求件数304件、決定件数362件)、認定率はまたもや低い23.4%だった。大阪では2023年10月より過労死事案の審査を大阪労働局内の「高度労災補償調査センター」から各労働基準監督署で担当するように運用を変更しており、以後処理スピードは上がったものの、認定率が低下しているのはずさんな審査による不支給決定が増えている疑いがある。
時間外労働時間別支給決定件数では、100時間以上120時間未満が74件で一番多い。精神障害の労災認定では長時間労働以外の心理的負荷による認定も多く、時間外労働が多くなくても認定されている事案も多い。ただ労働時間以外の「その他」と分類された件数が615件あり、これは「特別な出来事」か労働時間を調査するまでもなく明らかに労災と認められた事案ということで、支給決定件数のうち60%がここに該当している。
カスハラは3番めに多く
最後に出来事別の支給決定件数だが、「パワーハラスメントを受けた」が224件(決定件数389件、認定率57.5%)で最多だった。前年の157件から67件増加した。2位は「仕事内容・量の変化を生じさせる出来事があった」で119件(決定件数358件、認定率33.2%)、3位「顧客や取引先からの迷惑行為を受けた(カスハラ)」108件(決定件数207件、認定率52.1%)、4位「セクシュアルハラスメントを受けた」105件(決定件数191件、認定率54.9%)、5位「悲惨な事故や災害の体験・目撃」87件(決定件数145件、認定率60%)だった。今回もハラスメントに関する出来事が多くを占め、パワハラ、セクハラ、カスハラを合計すると437件で全体の4割以上である。またハラスメントではなく、上司や同僚とのトラブルと判断されて不支給となった事案も多い。特に「上司とのトラブル」は決定件数が953件にもかかわらず、支給決定件数は38件で認定率3.9%、「同僚とのトラブル」は支給4件で決定件数は217件、認定率は1.8%だった。
労働者にとって深刻な労働問題である「退職を強要された」「転勤・配置転換があった」といった出来事でも認定件数が少なく、退職強要は18件で決定件数67件、認定率26.8%、配置転換は21件、決定件数132件、認定率15.9%だった。
2023年9月に精神障害の労災認定基準が改定されたが、2024年度の労災補償状況にその影響は出ていただろうか。ハラスメント関係の出来事での認定は件数は増加した。しかし、これはここ何年も続いているので、改定によって増加したとは言えないだろう。ただカスハラについては、出来事として新設されたため、この項目で多くの事案が認定されたことは改善された点だろう。ただ、依然として精神障害、脳・心臓疾患の労災認定率は低く、被災して体調が悪い中、さらに労災請求という困難に苦しく被災者は後を絶たない。
今回の労災補償状況を踏まえ、今年中に再度厚労省交渉を持つ予定である。
関西労災職業病2025年7月567号

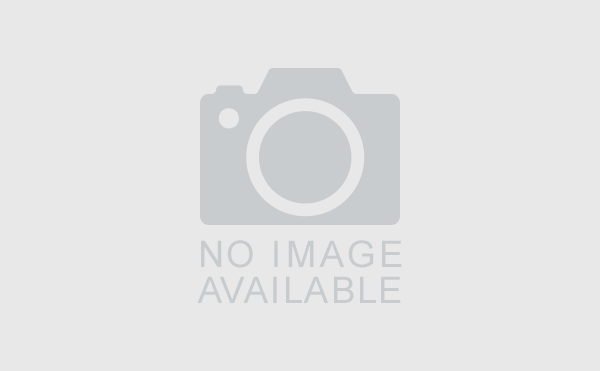
コメントを投稿するにはログインしてください。