低線量の放射線被ばくの影響がより鮮明に~原子力施設のがん死疫学調査(INWORKS2023)が示すもの
100mGy未満でも有意な過剰相対リスク増加
低線量の放射線被ばくが人体に及ぼす影響をどう評価するかについて、大規模な疫学調査の最新報告が注目されている。2023年8月に発表された「国際核(施設)労働者調査」(INWORKS:International Nuclear Workers Study)だ。
世界で最も大規模で確かな情報の多い米英仏3か国の13の核施設と原子力機関のデータベースに登録された、総数309,932人の労働者の約70年(1944~2016)にわたる死亡統計と、その個人線量計のモニタリング記録に基づいた累積被ばく線量などのデータを統合して解析したというもの。
これまでの低線量被ばくの影響評価は、広島・長崎の原爆被爆者の寿命調査(LSS)の高線量被ばくによるデータをもとに、他の実験結果による知見をもとに推計したものであるのに対し、INWORKSの疫学調査は、線量計で個人の被ばく線量が確実にモニタリングされている被ばく集団について、情報がしっかりしている米英仏の原子力施設の労働者集団を統合した大規模調査だ。しかも電離放射線への長期にわたる低線量率・低線量被ばくを受けた集団を、何十年もの間フォローした結果を解析した結果である。このことからINWORKSの疫学調査結果は、現在の放射線規制の根拠となっている影響評価を検証するに足るものと評価されている。
INWORKSの2023年の報告論文の主な内容は以下のとおりだ。
1)外部被曝による蓄積線量(結腸線量に換算)に応じて、全がん死、固形がん死のリスクが増大し、その線量あたりの過剰相対リスク(ERR/Gy)の増加は統計的に有意であった。
2)固形がん死の線量・影響関係は「直線関係」である。(図1)
3)1)、2)については、100mGy未満でも、さらに50mGy未満の低線量域に限っても、固形がん死について、統計的に有意なリスク増加が認められた。
4)広島・長崎の原爆被爆者の寿命調査(LSS)と比較して、INWORKSのERR/Gyは、統計的に同じ程度の値ではあるが、むしろ高かった。INWORKSでは、低線量率・低線量被曝での「リスクの低減」の証拠は認められなかった。
5)以上の結果は、今後の「放射線防護」の基準の議論に重要な情報を提供するものである。
注)固形がん:白血病など血液・造血系の悪性腫瘍以外のがん

労災認定基準に影響必至
線量当たりの相対過剰リスクの増加が統計的に有意であり、しかも100mGy未満、50mGy未満の低線量域でも統計的に有意なリスクの増加が認められるという報告は、現在の放射線被ばくによる労災認定に大きな影響を及ぼすことになる。
厚生労働省が低線量被ばくによるがん死亡についての根拠とするUNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会)の報告は次の通りだ。
- 統計学的に有意なリスクの上昇は100から200mGyまたはそれ以上で観察される。
- 被ばく線量が100mSvを超えるあたりから、被ばく線量に依存して発がんのリスクが増加する。
- 放射線による発がんリスクの増加は、100mSv以下の低線量被ばくでは、他の要因による発がんの影響よって隠れてしまうほど小さく、放射線による発がんのリスクの明らかな増加を証明することは難しい。
これにもとづいて、業務上外の判断をすることとしており、例えば2020年3月に脳腫瘍の労災請求があった際に公表された「当面の労災補償の考え方」は次の通り。
「1 当面の労災補償の考え方
放射線業務従事者に発症した脳腫瘍の労災補償に当たっては、当面、検討会報告書に基づき、以下の2項目を総合的に判断する。
(1) 被ばく線量
被ばく線量が100mSv以上から放射線被ばくと脳腫瘍発症との関連がうかがわれ、被ばく線量の増加とともに、脳腫瘍発症との関連が強まること。
(2) 潜伏期間
放射線被ばくから脳腫瘍発症までの期間が5年以上であること。
2 その他具体的検討
個別事案の具体的な検討に当たっては、厚生労働省における「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」において引き続き検討する。」
現在の固形がんについての労災認定は、「統計的に有意なリスクの増加」が認められる累積線量100mSv以上で業務上と判断しているわけだ。この論理でいくと、INWORKSの100mSv未満でも有意なリスクの増加があるのだから、有意差を認めて業務上認定の道を開くべきということになる。
この点について検討会では昨年7月1日に検討を行い、次のような結論に至ったことをHPで公表している。
- INWORKSのデータは科学的に大変興味深いものである。
- UNSCEARを中心とした、これまでの多くの論文とは異なる内容がある。
- 喫煙の交絡の可能性について間接的な評価となっていることや、診断・治療における医療被ばくの情報が収集されていない等の指摘がある。
- UNSCEARあるいはICRP(国際放射線防護委員会)は、広島、長崎、INWORKS等の様々な文献を総合的に判断、考慮して防護体系あるいは報告書を作っているため、この報告書によって、かなりの確度で低線量の被ばくによる影響があるとなれば、ICRPは防護体系の基準を考え直すことや、UNSCEARが取り入れるかもしれない。
- INWORKS2023報告は、1つの研究結果であり、研究結果を注視する必要はあるが、この結果1つで労災補償の考え方を見直すと結論づけるのではなく、今後も国際的な知見を収集するとともにUNSCEARやICRP等の国際機関の報告書を踏まえて判断していくことが重要である。
これまでにない低線量被ばくの影響に関する確かな科学的知見が示されたことの意義は大きく、今後のICRPやUNSCEARの議論を待つまでもなく、労働者保護の立場から、労災認定基準の運用は速やかに改めるべきということになるだろう。
線量・線量率効果係数(DDREF)は1
被ばく限度は現行の半分が妥当?
またそもそもの電離放射線障害防止規則による放射線業務への安全衛生上の規制にも大きく影響を及ぼすことになる。なんといっても年間被ばく限度となる50mSv、5年の限度となる100mSvの根拠が大きく揺らいでいるのである。
INWORKS報告は、がん死の相対リスクと蓄積線量の関係は、全線量域で直線モデル(直線関係)で「適切に表す」ことができることを示している。ところがICRPは「低線量域のほうが高線量域に比べて、線量当たりのリスクが低い」(つまり傾きが緩やかになる)として線量・線量率効果係数(DDREF)を2と決めて、低線量の影響評価に反映している。つまり、100mSv以下の影響について、相対リスクを2で割ってしまう、つまり2分の1に切り下げるというわけだ。
その2分の1の評価をもとに、20歳から60歳まで仕事をする人を想定して、放射線の影響により余命を短縮する年数が許容できる範囲か否か、他の労働災害による余命損失を比較して算出したのが、年50mSv、5年で100mSvという数字である。
つまり、DDREFが2は間違いで、実際は直線関係(DDREFは1)ということになるのなら、単純に考えて年間の被ばく限度は25mSv、5年で50mSvに改正するべきということになるのだ。
これからの動きにおおいに注目するべきと言えるだろう。
関西労災職業病2025年7月567号

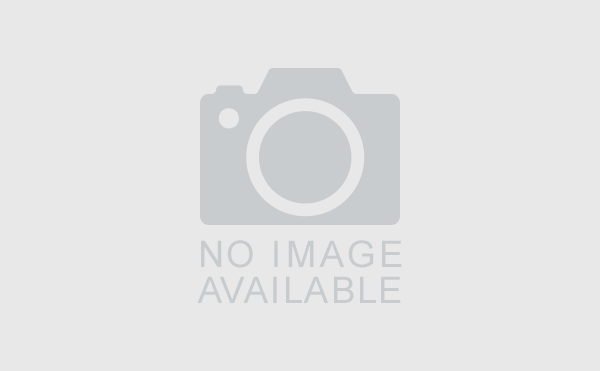
コメントを投稿するにはログインしてください。