「安全帯」から「要求性能墜落制止用器具」へ~6.75m以上はフルハーネス型が義務
労働安全衛生関係法令から「安全帯」という言葉がなくなり、「墜落制止用器具」に替わってからずいぶん時間が経った。2018年の政省令改正で入れ替わり、改正前の構造規格による安全帯の使用が認められる移行期間も2022年1月1日で終わっている。
死亡災害で最も多いのは「墜落・転落」であるという状況は、ここ10年以上続いており、近頃は減り止まり現象さえ見られ、死傷災害の件数でも、ベスト3にランクインしている。第14次労働災害防止計画においても重点項目として挙げられ対策が強化されているところだ。最後の砦であるはずの墜落制止用器具について、効果を確かなものとするべく省令改正が行われたのは当然といえる。
以前の安全帯といえば、一本つりの胴ベルト型の胴ベルト型とロープの張力を利用して体を支えるU字つりと決まっていて、作業の種類に応じてどちらかを着用するのが普通だった。しかし胴ベルト型を使用した状態での墜落時に、ベルトの圧迫により内臓を損傷したり、ずり上がって胸部を圧迫することによる窒息などが起きる危険性が指摘され、実際に災害事例が確認されている。U字つりについては、そもそも墜落を制止する機能は不確かで、墜落災害が起きている。また国際規格ではすでに、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数個所で保持するフルハーネス型が採用されていたことから全面的な改正となった。
大切なのは必要に応じた着用器具の選定
改正の内容は、墜落を制止する効果を確実なものとするため、これまでより具体的な作業内容に応じた使用を義務付けるものとなっている。そのため、法令上の表現も以前のように「安全帯」という単語だけで表記するのではなく、「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」(労働安全衛生規則第130条の5第1項)と表記されている。
あまりに長いので、労働安全衛生規則の最も若い条文である第130条の5より後の条文では「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する」を「要求性能」と省略して「要求性能墜落制止用器具」と表記されているわけだ。
その要求性能墜落制止用器具の使用が義務付けられている作業は、労働安全衛生規則で22の作業、クレーン等安全規則で7作業、ボイラー及び圧力容器安全規則、ゴンドラ安全規則、酸素欠乏症等防止規則で各1つ、合計で32の作業ということになる。
ここで問題となるのは、「墜落による危険のおそれに応」じて選ぶ墜落制止用器具の種類がどんなものかということだ。まず原則は、国際的な規格でもあるフルハーネス型ということになる。フルハーネス型は墜落制止時に身体に与える衝撃が比較的小さく、ベルトから抜け落ちるなどの事故も起こりにくいなどリスクが小さいため、まず原則とされている。
しかし、着用者が墜落時に地面に達するおそれがあるような高さ以下の作業では、フルハーネス型ではなく、胴ベルト型が適切ということになる。では、どの高さ以下で胴ベルト型のほうが適切なのかという判断をどうするかということになる。これを判断するにはまず、ランヤード(図参照)の長さとフックの取り付け高さがいくらかということになる。そしてショックアブソーバーの伸びの最大値をプラスし、さらに1メートルの余裕をみると、高さ6.75メートルという数字が出てくる。

墜落制止用器具の選定要件は、まず第一に、6.75メートルを超える箇所ではフルハーネス型を必ず選定することである。一般的な建設作業の場合は5メートル以上、かつてのU字つり使用が一般的だった柱上作業では、2メートル以上でフルハーネス型使用が推奨されている。
墜落制止用器具は着用者の体重や装備品の重量に耐えるものである必要がある。
また、衝撃を吸収するショックアブソーバーは、腰の高さ以上にフックを掛ける場合は第一種、足下にフックを掛ける必要がある場合は第二種と、墜落時の衝撃に応じたものを選定する必要がある。
こうした選定の要件などを含め、フルハーネス型が義務となる高所作業を行う労働者については、合計6時間の安全衛生特別教育を受けることも義務化されている。
取り組みと職場での点検を進めたい。
関西労災職業病2025年4月564号
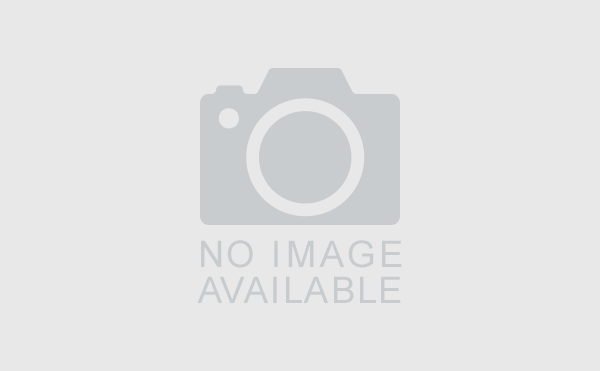

コメントを投稿するにはログインしてください。