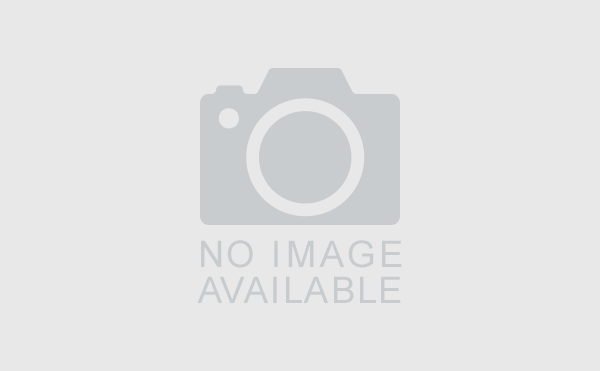メンタルヘルス・ハラスメントテーマに厚労省交渉【付:(メンタルヘルス、ハラスメントにかかる)労働安全衛生・労災補償に関する要望書2025/3/30】/全国労働安全衛生センター連絡会議

労働相談の中でも職場でのハラスメントに関する相談が非常に多く、行政の相談窓口、各労働組合、全国の労働安全衛生センターでも対応に労力が割かれている。長時間労働も含めた職場での業務や精神的負荷によるメンタルヘルス問題も多く、被災者への対応のみならず、職場での予防対策が必要とされている。しかし、メンタルヘルス対策、ハラスメント防止対策は、大企業では制度が整えられつつあるものの、実態が伴わない、あるいはうまく機能していないということも見受けられ、中小企業では対策できる資力や人材不足で取り組みが遅れている。
全国労働安全衛生センター連絡会議(全国安全センター)では、メンタルヘルス・ハラスメント対策局で定例会議を行い、各センターで取り組む事例を共有し、制度の問題点を洗い出し、現状改善のための議論を行っている。そこから出た意見を要望書(本稿末参照)にまとめ厚生労働省に提出し、立憲民主党の阿部知子衆議院議員の仲介で、5月27日に衆議院第一議員会館にて交渉を行った。要望の内容は、労災補償状況の詳細や分析、認定基準の運用方法、ハラスメント相談窓口やメンタルヘルス対策などだった。
要望が多岐にわたったため厚労省側からは、労働基準部補償課、監督課、保険課、雇用環境・均等局、労働安全衛生課などから約20人が対応に出てきた。全国安全センター側は東京、神奈川、名古屋、大阪、兵庫から12人ほどが参加した。
補償状況のデータを元に分析を
厚生労働省は過労死等の労災補償状況を毎年公表している。発表内容には含まれていない部分についてデータの提供を求めた。データ部分で回答可能なものについては、交渉日の前に文章で回答をもらったうえで、当日、さらに質問する形となった。
脳・心臓疾患の支給事案のうち、「長時間の過重労働」「短時間の過重労働」「異常な出来事」の内訳は、「長時間」が190件と一番多いが、「短時間」が15件、「異常な出来事」が11件と少ない件数ではあるが認められていることが分かった。ただし、支給決定件数のみしかデータ提供がなかったため、認定率は分からなかった。また長時間労働のうち5件は複数業務要因災害ということだった。
精神障害で「特別な出来事」があったとして認定されたものの内訳では、やはり「月160時間以上の残業」などの極度の長時間労働で認められたものが32件と一番多く、「強姦などのセクハラ」が17件と二番目に多かった。負荷評価表にある出来事の中でも「セクハラ」は三番目に多く、現在も職場でのセクハラは深刻な状況であると考えられる。
また、決定件数のうち、「専門部会」で決定したのは421件、うち支給は115件、「専門医の意見」での決定は1796件、うち支給410件、「主治医の意見」での決定は363件、うち支給は358件だった。精神障害の認定基準ができた当初は、すべての事案が「専門部会」の合議で判断されていた。ところが現在は2580件のうち421件のみとなっている。ただし、専門部会で判断する場合は、事案の内容が複雑であったりして、認定率は30%を切っている。決定件数の一番多いのは「専門医の意見」であり、こちらはわずか22%しか認定されていない。主治医の意見で判断された事案は以前より増えており、その場合はほとんどが支給決定される。審査期間も短縮されるので、なるべく主治医の意見で決定されることがこちらとしては望ましい。
集計していないとして、厚労省から答えが得られなかった質問に「2023年度における、精神障害の障害補償支給の件数とその発症から症状固定までの療養期間ごとの内訳、および障害等級別の件数を明らかにすること」がある。質問の意図としては、精神障害の症状固定では、まだ寛解に程遠く、治療が必要なのに打ち切られた事案や、10年20年労災での療養が続いている事案もあり、各労働局でも判断にばらつきがあるので、療養期間や障害等級を知れば、どのように運用されているのかも把握することができるし、本省でも現状把握してほしいということだ。こちらからは具体的な事案もあげて、集計するように口頭でも要望した。また負荷評価が「中」の出来事が複数あって認定となった事案についても集計がないとのことだったが、これについても、集計して、分析することの重要性を説明して要望した。
精神障害で2020年以降「医療・福祉」業種での支給決定件数が急増していることについて原因を訪ねたが、理由は不明としながらも出来事としては、「悲惨な事故や災害の体験」と「カスハラ」などによる支給決定が増えているということだった。2倍、3倍という増加率なので、きちんと分析して合わせて対策を行うべき状況であると念を押した。
都道府県ごとに労災認定率に大きな差があることについては、これまでと同じく適切に判断した結果であるとの回答だったが、やはり、常に低い認定率というのは何か原因があるという目で見て、内容分析すること、また研修などで事例の共有などを行って判断のばらつきをなくしていくことなどを要請した。
負荷を「強」とするべき内容のセクハラ事案で、被災者が加害者に迎合したことや事業者が事実上救済となっていないような対応をしたことなどを加味することによって、負荷評価を軽く判断することがあり、判断する職員のセクハラへの認識も不十分であり、セクハラの負荷強度を見直すように求めた。
医療機関の無理解問題
精神障害の労災請求で、医療機関が労災の請求書に証明をしないというトラブルが度々起きている。休業補償請求書には医師が病名や就労できなかった期間を証明しなければならない。「労災指定機関ではない」「会社とのトラブルを避けたい」などと証明を拒否し、労災にするなら転院するよう求める医療機関もある。被災者は請求書さえ作成できず、請求をあきらめることになりかねない。労働者に医療機関の証明欄の記載が無くても請求できることを周知すること、また医療機関に対しては、労災指定でなくても、書類の作成に協力すること、労災請求することで診療を拒否することがないように厚労省が周知徹底することを求めた。
他には、専門性のあるワンストップで対応できるハラスメント相談窓口を設けること、ストレスチェック制度について、集団分析の義務化と安全衛生委員会での結果の共有で職場改善の実効性を確保することを求めた。
回答の多くは、適切に処理している、であるとか、ご意見として賜ります、であったが、対応に出てきた厚生労働省の係長クラスの実務担当者には、現場の実態をいくらかでも知ってもらえたと思う。いくらかは参考に集計方法を見直したいという答えもあった。今後も満足のいく回答が返ってこないとしても、職場の実態や被災者の現状を繰り返し訴えていきたいと思う。
労働安全衛生・労災補償に関する要望書
2025年3月31日
厚生労働大臣 福岡 資麿 様
全国労働安全センター連絡会議メンタルヘルス・ハラスメント対策局横浜市鶴見区豊岡町20-9 サンコーポ豊岡505
事務局 TEL 045-573-4289
FAX 045-573-1948
(担当 川本)
貴職の日ごろのご活動に敬意を表します。
全国労働安全衛生センター連絡会議(メンタルヘルス・ハラスメント対策局)は、貴職にたいして下記の要請をいたします。よろしくご回答いただきますようお願い申し上げます。
記
1 脳心臓疾患および精神障害の労災補償について
(1)2024年(令和6年)6月28日付で公表された『令和5年度 過労死等の労災補償状況』(「脳・心臓疾患の労災補償状況」および「精神障害の労災補償状況」)について、以下の追加データを明らかにすること。なお、下記のデータについては、今回の要望に関する交渉に先立ってデータを提供すること。
- 「脳・心臓疾患の労災補償状況」について、労災認定基準に定められた「長時間の過重労働」、「異常な出来事への遭遇」、「短時間の過重業務」の認定要件ごとの請求件数、決定件数、支給件数の数字を明らかにすること(「脳・心臓疾患の労災補償状況」に記載なし)
- 「脳・心臓疾患の労災補償状況」における脳・心臓疾患の支給決定事案のうち、時間外労働が80時間未満だったものや「短期間の過重業務・異常な出来事」で認定されているもの(令和5年度は計69件、表1-6)について、評価された労働時間以外の負荷要因の内訳を明らかにすること
- 「精神障害の労災補償状況」のうち、「特別な出来事」で支給決定されたもの(令和5年度は計71件、表2-8)について、その内訳(生死にかかわる極度の苦痛・労働不能な後遺障害を残す病気やケガ、業務で他人を死亡・重大なケガ病気を負わせた、強姦などのセクハラ、その他、月160時間以上の残業など長時間労働の各項目)と各件数を明らかにすること
- 「精神障害の労災補償状況」の表2―8に関連して、出来事が複数あって支給決定になっている場合で、心理的負荷評価「強」の出来事がなく、「中」が複数あって総合評価を「強」と判断して支給決定した件数とその出来事の内容を明らかにすること
- 「精神障害の労災補償状況」の決定件数(令和5年度は計2583件、表2-1)のうち、専門部会で判断したもの、専門医の意見で判断したもの、主治医の意見で判断したものの各決定件数と、支給・不支給件数を明らかにすること
- 2023年度(令和5年度)における、精神障害の障害補償支給の件数とその発症から症状固定までの療養期間ごとの内訳、および障害等級別の件数を明らかにすること(「精神障害の労災補償状況」には記載なし)
- 「脳・心臓疾患の労災補償状況」および「精神障害の労災補償状況」の両方について、複数事業労働者につき業務上と認定されて支給決定されたものの件数を明らかにすること(「脳・心臓疾患の労災補償状況」および「精神障害の労災補償状況」には記載なし)
- 「精神障害の労災補償状況」において、「感染症など病気や事故の危険性が高い業務に従事した」として、支給決定された2件(表2-8)の概要を明らかにすること
(2)精神障害の業種別支給決定件数で、「医療・福祉」が、2019年の78件から2020年は148件に急増しており、その後も増加し2023年は219件だった。増加した事案内容・理由を明らかにすること
(3)精神障害の労災認定請求、決定、支給件数について、あまりにも支給決定の占める割合が都道府県労働局によって異なるので、その理由を説明すること。(具体的には令和5年度において、北海道では99件のうち45件が支給、福岡では85件のうち41件が支給である一方で、京都は81件のうち20件が支給、神奈川は204件のうち50件が支給となっている。)
(4)精神障害の労災調査において、パワーハラスメントが原因であると請求人が主張した事案で、具体的出来事表のパワーハラスメントの項目ではなく、「上司や同僚とのトラブル」の項目に該当するとされて、不支給決定を受ける事案が続出している。労基署が、各事案において具体的出来事表への当てはめ方を判断する際に、「上司や同僚とのトラブル」に該当するのか、上司等からの「パワーハラスメント」に該当するのかを判断する際の判断基準について明らかにすること。
(5)精神障害の心理的負荷として、納得できない解雇はすべて「退職強要」であると判断すること。もし、そうではないとすればその理由を明らかにすること。
(6)精神障害の心理的負荷として、セクシュアルハラスメントの平均的な心理的負荷を「強」とすること。
また、心理的負荷評価表のセクシュアルハラスメントの例示のなかで、セクハラ行為が「継続して」いるか否かが、「中」か「強」の判断要素となっているが、ここでいう「継続」性の回数、時間ないし期間についての目安を明らかにすること。
具体例として、①東京労働局管内の監督署で、社長から職場の歓送迎会後の帰宅途中のタクシー内や連れていかれた小料理屋で肩を抱かれたり手を握られたりしたこと(計約2時間半)が、セクシュアルハラスメントであり、「数時間にわたって行われたもの」として「強」と評価され支給決定された(復命書による)という事案がある。②一方で、やはり東京労働局管内の監督署で、約2ケ月間にわたって何度も、職場で正社員から二の腕をもまれたり、手のひらを指でこすられるなどした(加害者は聴覚障がい者であり、これは手話の隠語で「エッチしよう」と言う意味、被害者も手話が理解できる)ことについて、監督署担当者の説明によると、セクハラだが「強」ではないとして不支給となった事案がある。なお、前者の事案について社長は酔っていてあまり覚えていないが謝罪している。後者の事案は、本人が会社に申し出た結果、事実関係を認めたようで、セクハラとして懲戒処分されている。
(7)医師の宿直業務について、患者への対応などの業務が発生した時間のみを労働時間としていることが多いが、仮眠していたとしても、何時でも対応する必要性があり、完全に業務を離れる状況ではないので、原則として労働時間とすること。
(8)近年、東京労働局では、精神障害の労災申請事案の調査を専門に行う調査班を設置しているが、急増する申請数に調査が追い付かず、申請の受理から決定まで1年前後かかるようになっている。労災保険法に規定された「被災労働者の迅速な救済」がまったくなされてない異常な事態である。厚生労働省は、東京労働局に対し、事態の改善のため、人員の増加や体制の見直しなどを早急に行うよう指示すること。
2 労災申請に関連する健康保険組合や医療機関の対応について
(1)全国健康保険協会(協会けんぽ)や各健康保険組合において労災職業病の紛れ込みを防ぐためのチェックが厳しくなっている。その中で、労災支給調査に時間がかかる疾病で休業を余儀なくされる場合、傷病手当金の請求と労災保険休業補償請求の二者択一を迫る誤った運用が(とりわけ一部健保組合で)しばしば見受けられ、労災請求をあきらめる被災者が出ている。
厚生労働省として、協会けんぽや各健康保険組合に対し、「請求者が労災請求中であることを健康保険組合等に伝え、労災支給時に返還する念書を提出すれば足りる」という点を、改めて通知すること。
(2)精神障害の労災申請において、「診療担当者の証明」の記載など申請手続きへの協力を断わる精神科医が続出している。具体的には、請求人が労災申請を相談した際に、「労災指定医療機関でなければ労災の手続きはできない」とか「会社とのトラブルを避けたい」などの理由を挙げて、証明を断ったり、転院するよう求めたりする精神科医が増えている。複数の心療内科から「労災の患者は当院では対応できない」と言われ、5つ以上の医療機関を転々とした当事者もいる。
厚生労働省は、労働者に対して、「診療担当者の証明なしでも労災申請は受理されうる」ことを周知すること。また、医療機関に対して(特に、心療内科やメンタルクリニックなどの小規模医療機関に対して)、「労災指定医療機関でなくとも、診療担当者の証明に協力すること」や、「労災保険の申請を希望する(あるいは労災保険を使用している)患者の受診を拒否しないこと」、「主治医は療養の事実を証明すればよいだけである」という点などを周知徹底すること。
3 職場のハラスメントの相談窓口について
(1)現在、職場のハラスメント問題に関する相談窓口としては、各都道府県の労働局の総合労働相談コーナーがあるが、専門の相談窓口ではなく、複雑かつ増加しているハラスメント相談の窓口としては十分に機能していない。弁護士などが配置され、労災補償や個別労使紛争(あっせん等)の相談も含めてワンストップで対応できるハラスメント特別相談窓口を設置すること
4 メンタルヘルスに関する予防対策について
(1)ストレスチェックの集団分析を義務付けるとともに、安全衛生委員会でその結果を共有して職場改善の実効性を確保すること。
(2)50人未満の事業所でのストレスチェック制度の導入は実効性が乏しく、むしろ労働者が、地域の産業医資格を持った精神科医師とのアクセスを容易にする仕組みを立案すること。
(3)労働時間の自己申告制を原則禁止するとともに、例外的に認める場合は、事業所の入退出記録やメール等の業務記録との相違について合理的な理由が判明しない場合、全てを労働時間とみなすようにすること。
関西労災職業病2025年6月566号