過労死等防止対策推シンポジウム2024/過労死防止大阪センター●大阪
11月の過労死防止啓発月間に行われる「過労死防止対策推進シンポジウム」が今年も、梅田のコングレコンベンションセンターにて11月18日に開催され、181人の参加者があった。過労死防止大阪センターは設立以来、大阪労働局とともにシンポジウムの内容を企画してきた。
今回のシンポジウムの前半は、大阪労働局から過労死防止対策の取り組み報告、3年ごとに改定が行われる「過労死等の防止のための対策に関する大綱(過労死防止大綱)」の今年の改正点について、過労死等防止対策推進全国センターの事務局長である岩城穣弁護士の解説があった。
大阪労働局の取り組みとしては、大阪府との「ノー残業デー」の取り組みや、時間外労働の上限規制について、自動車運転者、建設業、医師への周知、運送業については「荷主特別対策チーム」で荷主へ働きかけを行っていることなどを紹介した。
過労死防止大綱の改定では、時間外労働上限規制が全面適用となり、規制の遵守、指導の強化、またフリーランス等個人事業主の安全衛生対策の推進も盛り込まれた。調査・分析においても、芸術・芸能分野を重点業種に追加し、ハラスメント対策についても把握する。また新たに、カスタマーハラスメント対策を支援するとした。
休憩を挟んで後半は、池内裕美関西大学教授による基調講演「カスタマーハラスメントの現状と課題」だった。
今年は、カスタマーハラスメント対策が注目され、自治体で防止対策条例を制定したり、厚生労働省も防止対策を検討中である。
池内教授は、社会心理学者として悪質クレームを分析、その上で苦情対応の課題などを分かりやすく示した。クレームには、正当なクレームかつ手段が正当な場合の他に、正当な内容でも手段が不当、手段が正当でも内容が不当なクレーム、不当な内容かつ不当な手段の4パターンが有り、内容が正当かつ正当な手段でのクレーム以外は、カスハラとして対応するものとの分類をし、事例でこの4パターンを分かりやすく説明した。クレーマーの特徴やカスハラ増加の社会的背景については、消費者意識の向上、スマホやSNSで苦情を訴えやすくなり承認欲求形クレームが増えた、過剰なサービスによる過剰な期待、社会全体の疲労と怒りの沸点の低下などが影響しているとした。そして、苦情対応で相手をエスカレートさせないための注意点や、対応方法も説明した。クレーマーの心理の話は興味深く、対応についてもシンポジウムに参加した企業担当者は、大いに参考になったと思う。

最後は、それぞれ息子さんを過労自死で亡くした遺族2人が登壇し、二度とこのようなことが起こってほしくないという気持ちを訴えた。
関西労災職業病2024年11・12月560号

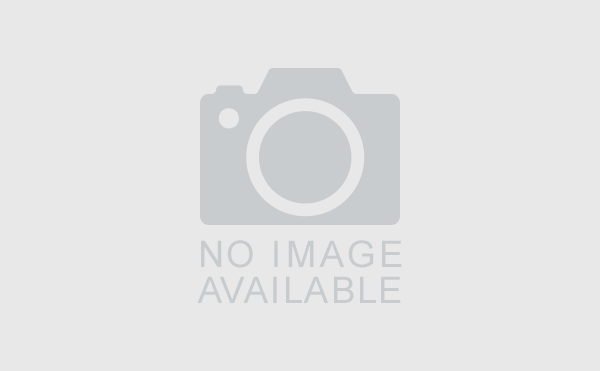
コメントを投稿するにはログインしてください。